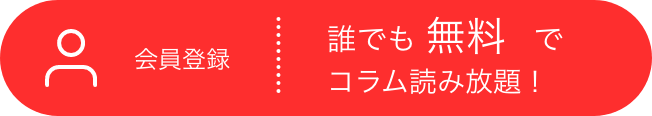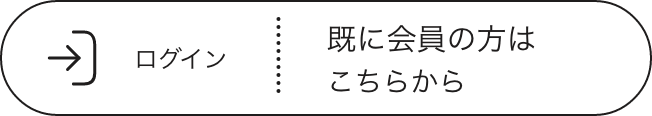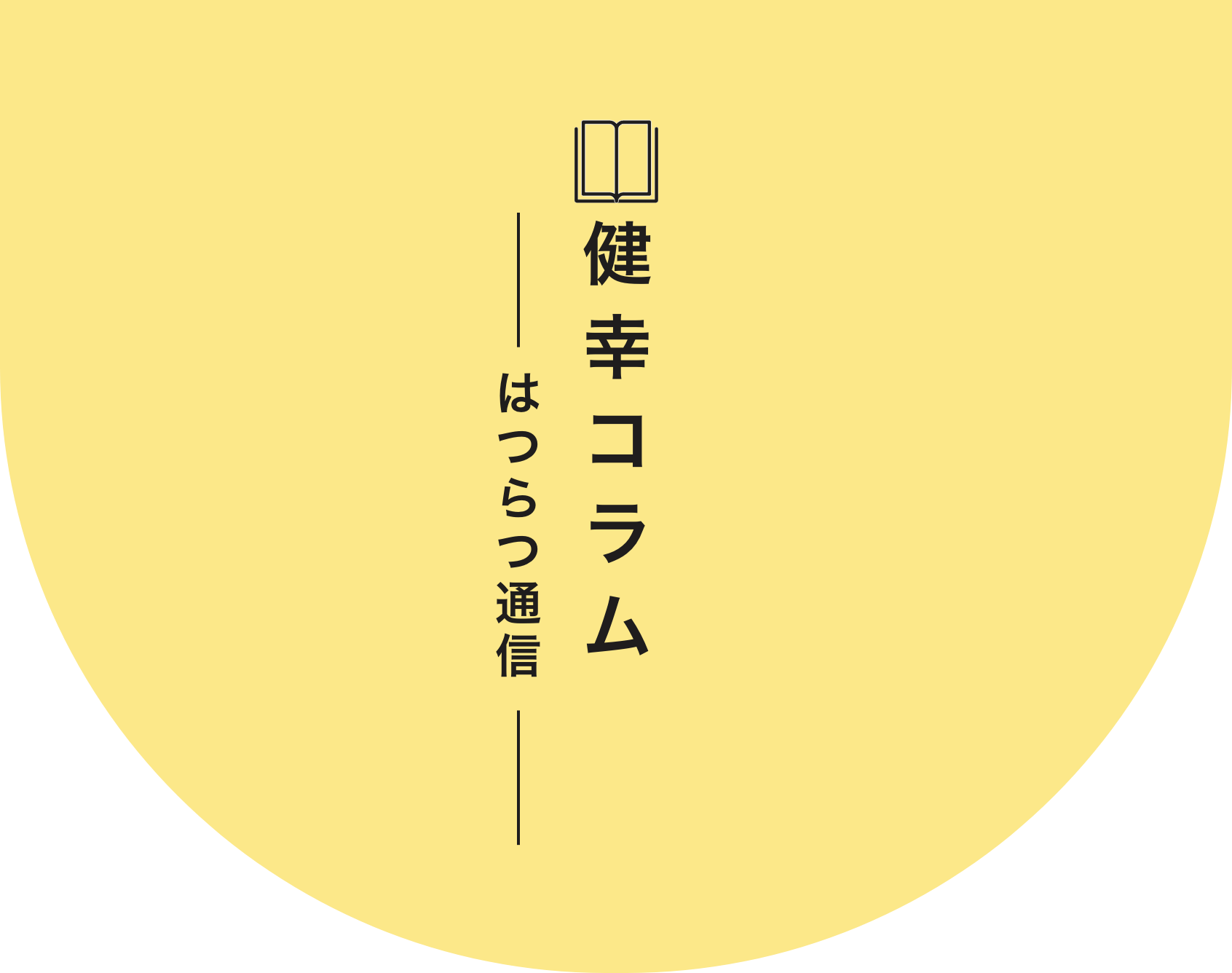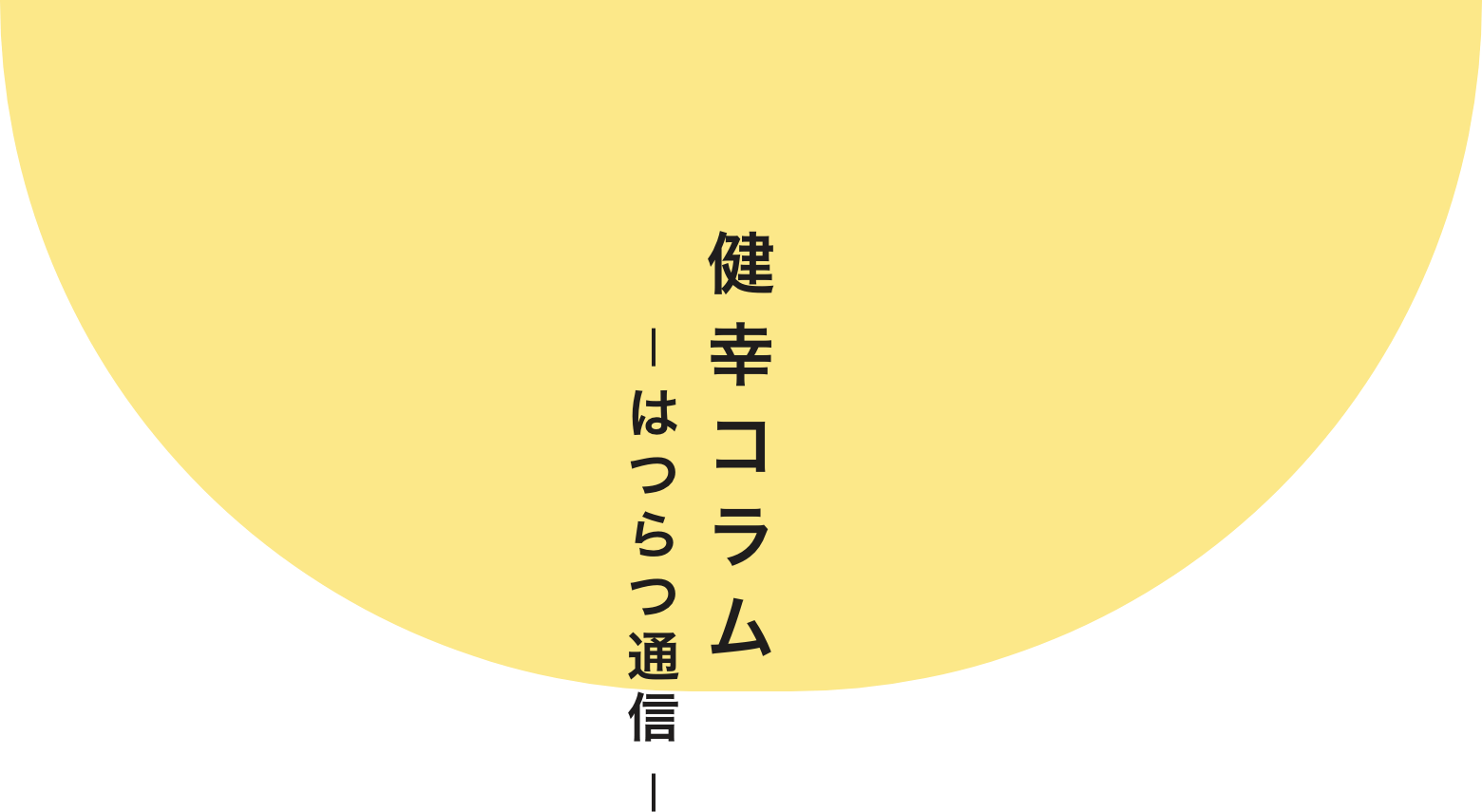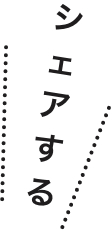④介護が始まるきっかけ
内閣府の「令和4年版高齢社会白書によれば、介護が必要となった主な原因は、「認知症」が18.1%で最も多く、ついで「脳血管疾患(脳卒中)」(15.0%)、「高齢による衰弱」(13.3%)です。このように、介護は病気やケガ、認知症の進行などによって始まることが多いようです。
親の介護は誰がする?
なんらかの事情で介護が必要になったとき、介護の義務があるのは、要介護者の配偶者や子ども、兄弟姉妹、祖父母などです。
民法では、「直系血族(直接親子関係でつながっている系統のこと)および兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある」、また夫婦に関しても「互いに協力し扶助しなければならない」と定めています。
つまり、「親の介護」を考えると、扶養義務を負うのは、親の配偶者、子ども、孫、親の兄弟姉妹ということになります。
なお2022年に実施した独自調査では、家族のうち親の介護をメインで行った人は、「長男」が29.1%で最も多い結果になりました。ついで、「長女」(20.2%)、「親の配偶者」(14.8%)と続きます。かつて、親の介護者の筆頭に上げられていたいわゆる「長男の嫁」は8.4%で、6番目です。
結果としては「長男」がトップであるものの、2番目は「長女」と、生まれ順が早い長男・長女の合計値は49.3%と約半数を占めました。「女性だけが担う仕事」とされてきた介護ですが、近年では男女問わず、子世代が「いつかは直面する課題」となっているようです。

引用
https://kaigo.homes.co.jp

- 監修/石渡 翔
- 社会福祉主事任用資格。リハビリデイサービスであるレコードブックで9年間介護とリハビリを学び、FC加盟店として横展開出来る店舗の基礎オペレーションを築く。介護における法改正の情報取得などコンプライアンス面の強みを生かして現在はエリアマネージャーとして複数店舗のマネージメントを担当。はつらつでも介護に纏わる情報を配信していきます。