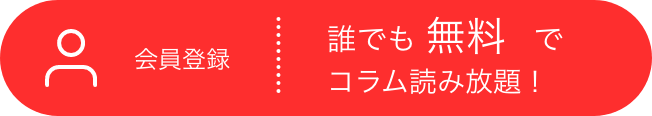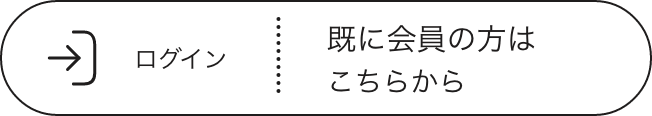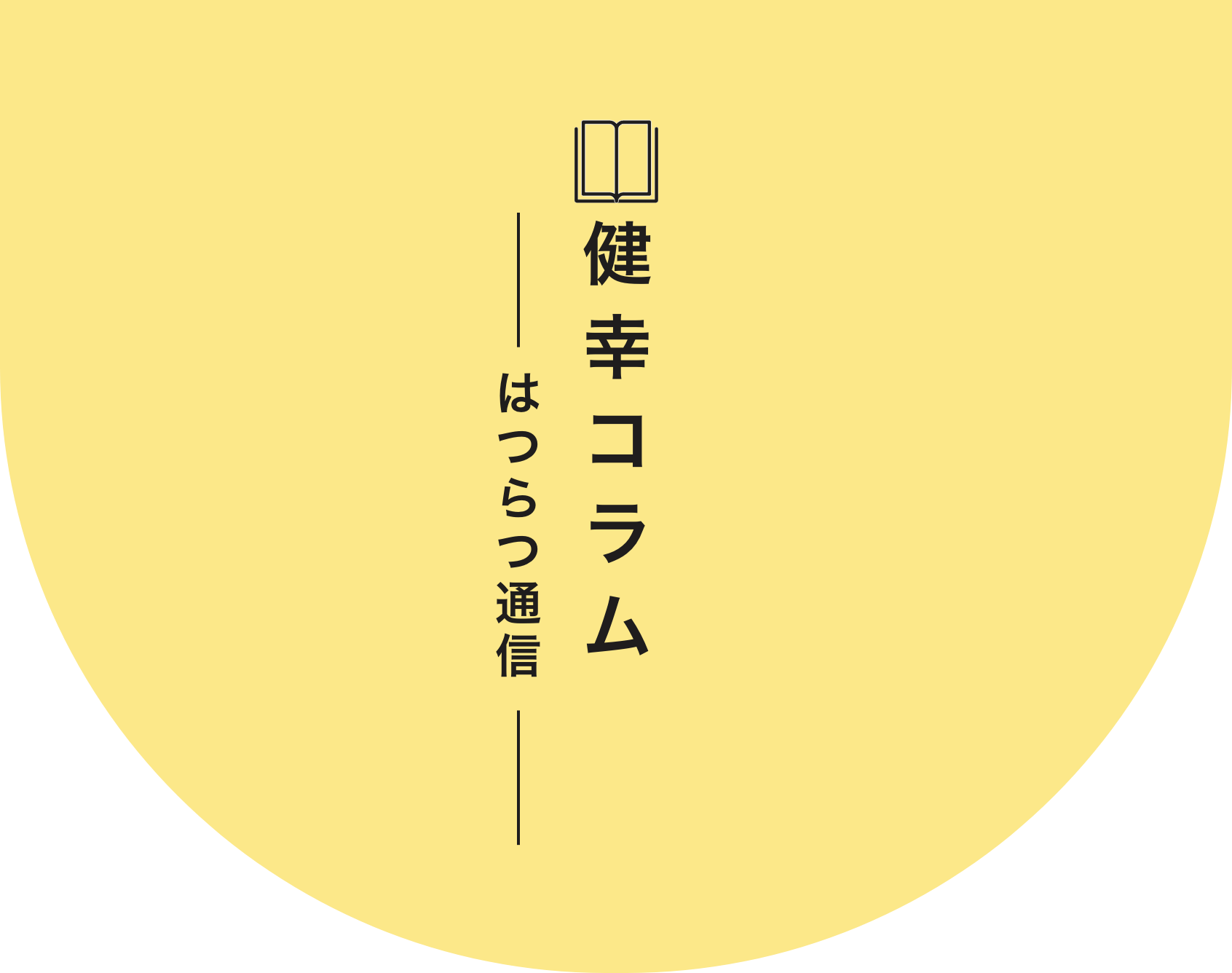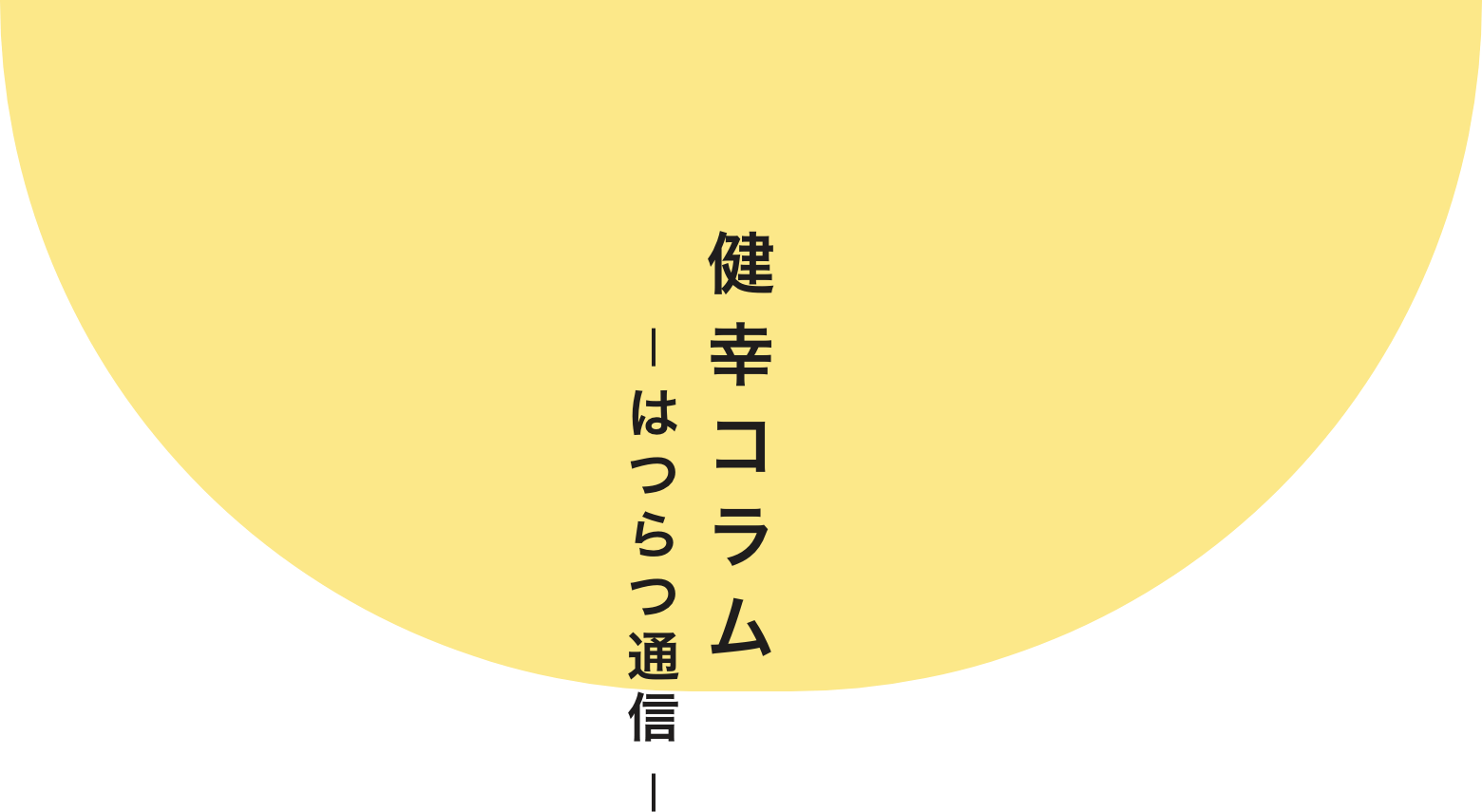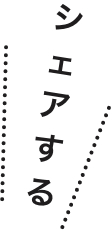🌟不穏を引き起こす原因は?
不穏の原因は、薬の副作用や離脱症状、せん妄などがあります。
さらに認知症の場合、
- 身体的苦痛
- 不安
- 苛立ち
などの精神的な原因も考えられます。
特に精神的な原因としては、環境の変化に順応できずに不安を感じる方が多いです。
認知症によって上手くコミュニケーションが取れないと、不安の増強につながります。
「不安であることを上手く表現できない」「対処法がわからない」などは、本人にとって大変苦しい状況です。
気持ちを周囲に理解してもらえない苛立ちから、攻撃的になり落ち着きがなくなります。
🌟認知症による不穏の対処法
・じっくり話を聞く
理解できない内容であっても、じっくり話を聞く姿勢が大切です。
話を聞くだけで行動が落ち着く場合もあります。
不安や不満はなかったか、行動の理由を本人から聞くようにしましょう。
ここをおろそかにすると「理解してもらえなかった」と感じ症状が悪化する可能性がありますが、「話せば理解してもらえる」と感じれば気持ちが安らぎます。
じっくり話すうちに漠然とした不安が具体化し、解決の糸口となる場合も多いです。
・安心できる環境作り
認知症の方は環境変化に不安を感じるため、できるだけ環境が変化しないように気をつける必要があります。
物質的な環境だけでなく、相談しやすい雰囲気や関係づくり、温かい声掛けなども重要です。
また、認知機能が低下すると安全な場所かどうかの判断が難しくなるので、具体的に今いる場所が安心できる場所であることを示すようにしましょう。
時間や日にちがわかりやすいように掲示したり、日課表などを用いると良いでしょう!
・身体の変化を確認する
身体的な苦痛が上手く表現できず、不穏として現れる場合があります。
本人の状態を細かくチェックし、身体的な異変の有無を必ず確認するようにしましょう。
食事の摂取量や睡眠状況などからも異変をとらえることができます。
・周辺の環境を確認する
認知症の方はその場で不安や思いを伝えることが苦手です。
不穏が見られた場合、周辺の環境を確認してみてください。
照明が明るすぎないか、室温やテレビの音量は適切か、不快に思う原因はないかという視点で環境を整えましょう。
心地よいと感じる環境作りが大切です!
・過ごし方を確認する
認知症の方は、何かに熱中し「楽しい」と感じている時は比較的穏やかに過ごすことができます。
退屈な時間を過ごしていると急に不安に襲われ不穏がみられる場合が多いです。
認知症の方の生活状況を、表情などからくみ取るようにしましょう。
また、どんな時に不穏がみられるか記録をとることもおすすめです。
原因が把握しやすく、対応がスムーズになります!

- 監修/榎戸あすか
- 2019年医療事務管理士免許取得。二次救急指定病院にてクリニック、入院病棟ともに4年間医療事務として勤務し介護業界へ転職。これまでの経験を活かしつつ、日々吸収していく情報をコラムで発信していきます!