健康長寿を支える和食〜まごわやさしい〜
日本の伝統的な食文化である「和食」。
2013年にはユネスコ無形文化遺産にも登録され、世界的にも高く評価されています。
その理由のひとつが、優れた栄養バランスと健康効果。
今回は「和食の栄養的な特徴」と「食生活に取り入れていきたい食材」をご紹介します!
①一汁三菜が生む理想的な栄養バランス
和食の基本は「一汁三菜」
主食・主菜・副菜に汁物を組み合わせる構成です。
- 主食(ご飯)‥エネルギー源となる炭水化物
- 主菜(肉、魚、卵、大豆製品)‥筋肉や血液など体を作るたんぱく質源
- 副菜(野菜、海藻、きのこ類)‥体の調子を整えるビタミン、ミネラル、食物繊維を補う
- 汁物(味噌汁など)‥発酵食品や具材で栄養をサポート
和食はこの基本の一汁三菜の構成にすることで、多様な食材を摂取でき、炭水化物・たんぱく質・脂質の三大栄養素に加え、ビタミン・ミネラル・食物繊維をバランス良く摂取することができます。
②低脂肪、良質なたんぱく質を摂取できる
和食では、魚や大豆製品などを使用するため低脂質で良質なたんぱく質を摂取できます。
魚に含まれるDPAやEPAは血液をサラサラにし、動脈硬化や心疾患の予防に有効です。
一方大豆製品からは植物性たんぱく質やイソフラボンが摂取でき、骨の健康やホルモンバランスの維持に役立ちます。
和食は油を多く使う料理が少ないため、脂質のとり過ぎを防げることも利点です。
③「だし」が支える減塩と満足感
和食の味の基盤となるのが「だし」。
昆布、かつお節、煮干し、干し椎茸等からとれるだしには、旨味成分(グルタミン酸、イノシン酸、グアニル酸)が含まれています。
この旨味によって、塩分を控えながらも味に満足感を得ることができるため自然と減塩につながります。
高血圧や腎疾患の予防を意識する上でも、旨味を活かした調理方法は有効です。

- 監修/和田 美里
- 管理栄養士。保育園で栄養士として給食業務や食育に従事した後に2018年介護業界へ転職。管理栄養士という資格を活かし、運動面と食生活面からお客様の身体にアプローチ出来るのが強み。
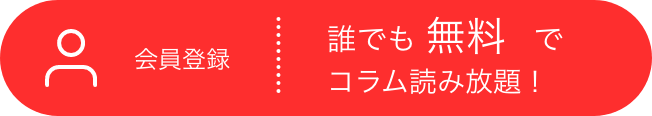
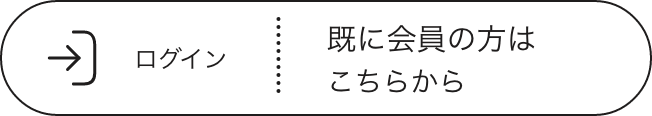
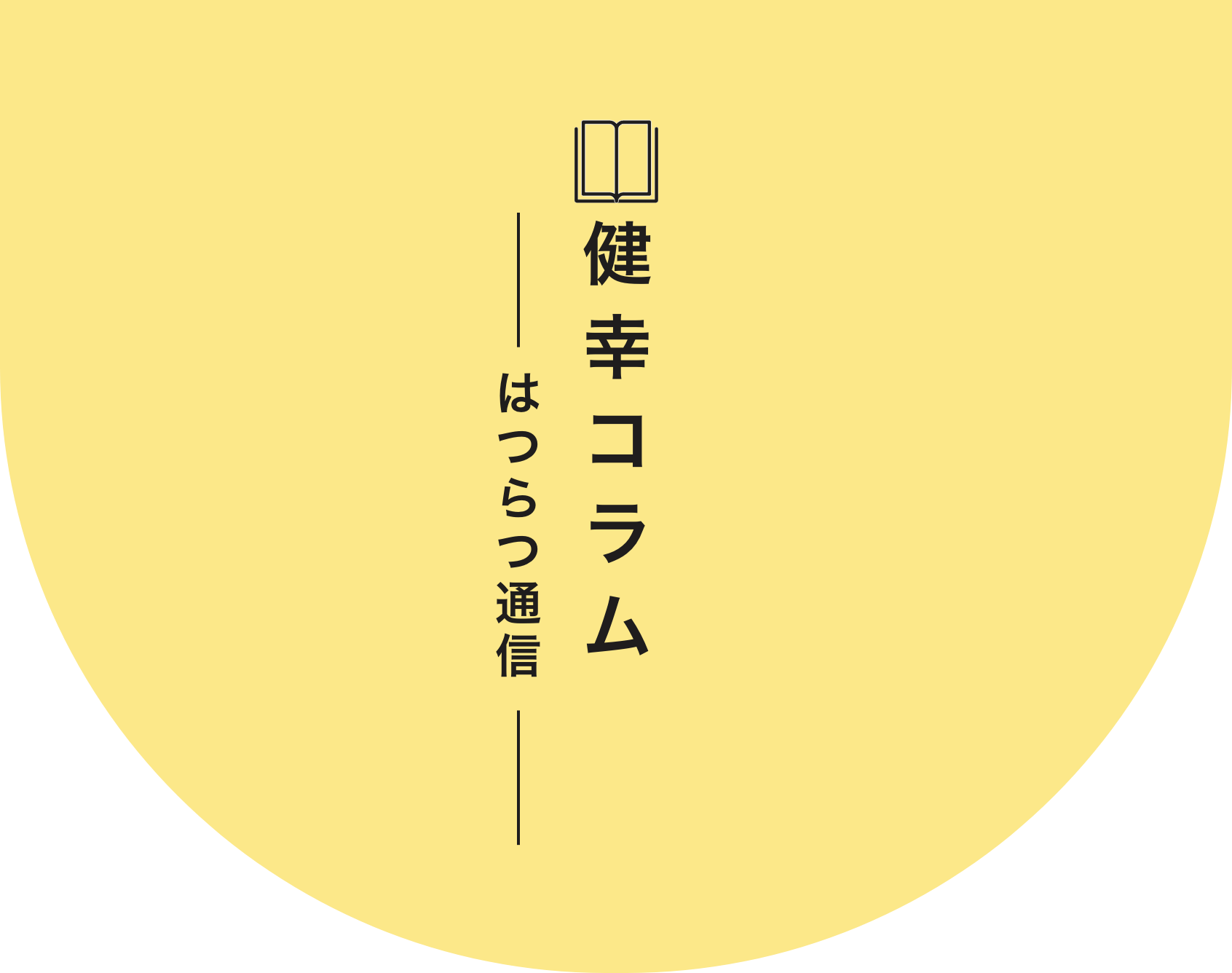
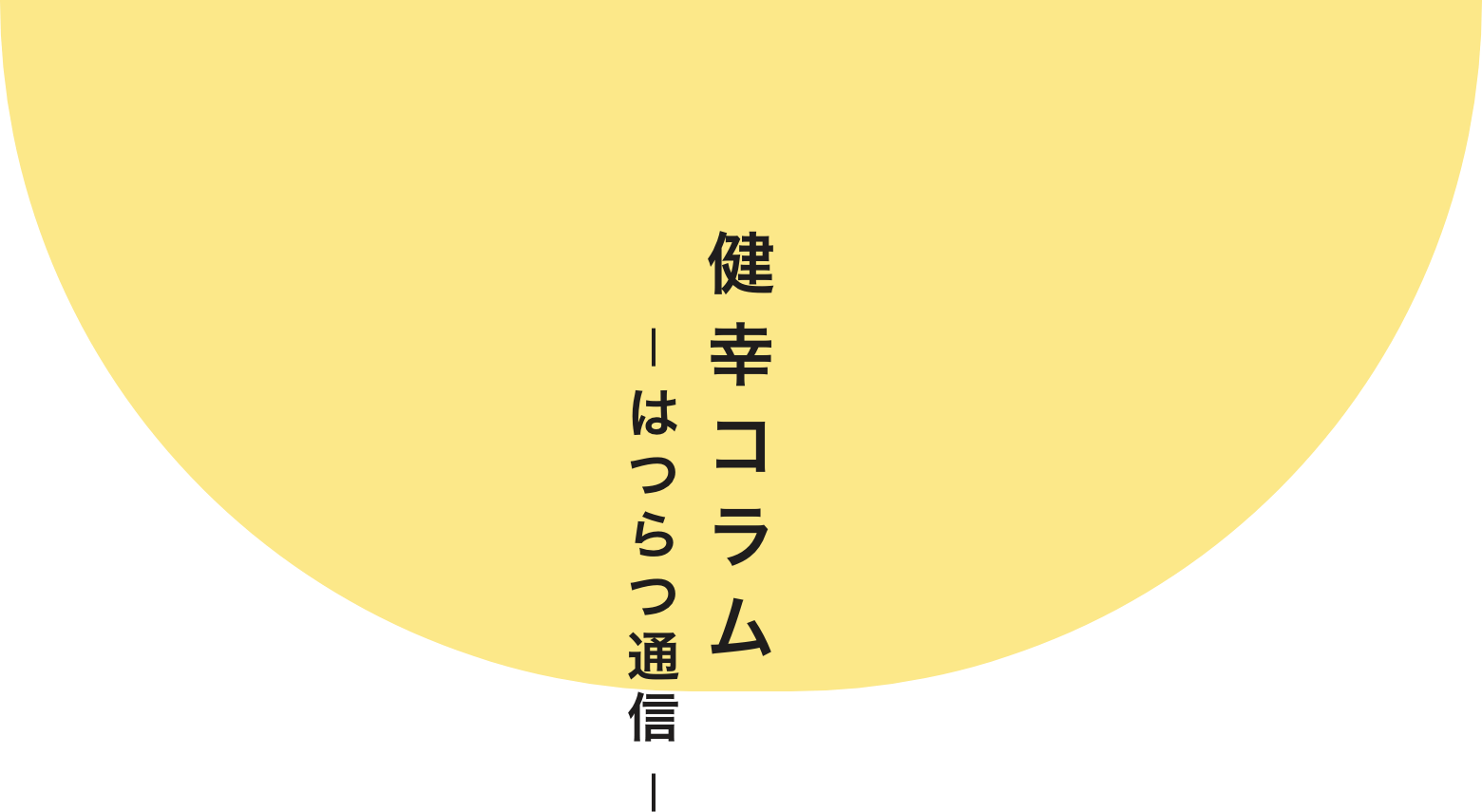

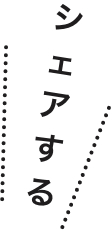


.png)